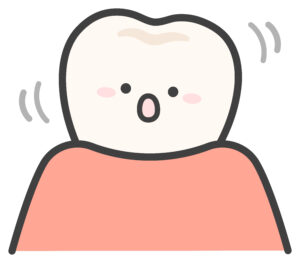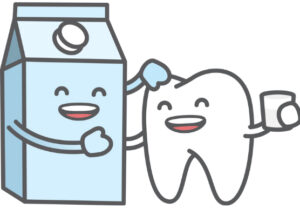「なんだか歯が浮いているような感じがする…」
「噛むと少し違和感がある、ムズムズする…」
こんな「歯が浮く感じ」、あなたも経験したことはありませんか? 一時的なものだと思って見過ごしがちですが、これは歯や歯茎からのSOSサインの可能性があります。放置すると問題が進行してしまうこともあります。
今回は、「歯が浮く感じ」の原因と、ご自身でできるケア、そして歯科医院での対処法について解説します。
なぜ「歯が浮く感じ」がするの? ~歯を支えるクッション「歯根膜」~
私たちの歯は、アゴの骨(歯槽骨)に直接固定されているわけではなく、「歯根膜(しこんまく)」という薄いクッションのような組織で支えられています。
歯根膜は、噛んだときの衝撃を和らげたり、食べ物の硬さなどを感じ取るセンサーの役割をしています。
「歯が浮いているような感じ」は、この歯根膜に何らかの負担がかかり、軽い炎症を起こして少し腫れた状態になることで生じると考えられます。歯根膜が腫れると、歯が少し押し上げられるように感じてしまうのです。
「歯が浮く感じ」の主な原因5つ
歯根膜に負担がかかる主な原因を見ていきましょう。
1. 歯周病(歯肉炎・歯周炎)
最も一般的な原因の一つです。歯磨きが不十分だと歯周病菌が増え、歯茎に炎症が起こります(歯肉炎)。進行すると歯を支える骨が溶かされ(歯周炎)、歯が不安定になります。
歯茎の腫れや骨の支えが弱くなることで歯根膜に負担がかかり、歯が浮く感じがします。自覚症状が少ないまま進行することが多いため、歯茎の腫れや出血があれば要注意です。
2. 食いしばり・歯ぎしり
寝ている間や日中の無意識の食いしばり・歯ぎしりは、歯に非常に強い力をかけます。この過剰な力が歯根膜にダメージを与え、炎症を起こして歯が浮く感じの原因となります。
3. ストレスや疲れ、体調不良
強いストレスや疲れ、風邪などで体の抵抗力が落ちていると、歯茎や歯根膜が炎症を起こしやすくなります。血行不良も影響し、歯が浮いたように感じることがあります。
4. ホルモンバランスの乱れ
特に女性の場合、生理前後や妊娠中、更年期などホルモンバランスが変化する時期は、歯茎が腫れやすく、歯が浮くような感覚が出ることがあります。
5. 歯の治療後
歯の神経を取る治療(根管治療)などの後、一時的に歯根膜が刺激を受けて軽い炎症を起こし、歯が浮く感じがすることがあります。これは治療に対する体の反応であることが多く、通常は数日から1週間程度で治まります。
その他: 歯の根の先に膿が溜まる「根尖病巣」、特定の歯に強く噛み合わせが当たる「咬合性外傷」、歯にヒビが入る「歯根破折」なども原因となります。
どうすればいい? 予防と改善のためのステップ
歯が浮く感じがしたら、原因に応じた対処が必要です。
ステップ1:セルフケアを見直す(プラークコントロール)歯周病予防・改善の基本は、毎日の丁寧な歯磨きです。
歯ブラシ: 歯と歯茎の境目に毛先をきちんと当て、軽い力で磨きましょう。
フロス・歯間ブラシ: 歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間の汚れは、デンタルフロスや歯間ブラシを使って必ず除去しましょう。
ステップ2:歯科医院でチェック&ケア(定期検診)
セルフケアだけでは限界があります。定期的に歯科医院でプロのチェックとケアを受けましょう。
定期検診: 3ヶ月~半年に1回程度が目安です。歯周ポケット検査や歯石除去、クリーニング、歯磨き指導などを受け、問題を早期に発見・対処しましょう。
ステップ3:生活習慣を整える
休息と栄養: 十分な睡眠とバランスの取れた食事で、体の免疫力を保ちましょう。
ストレス管理: 自分なりのリラックス方法を見つけ、ストレスを溜め込まないようにしましょう。
ステップ4:原因に合わせた対策
食いしばり・歯ぎしり: 歯科医院で相談し、必要であれば**ナイトガード(マウスピース)**を作りましょう。日中の噛みしめ癖にも注意しましょう。歯科治療: 根尖病巣や咬合性外傷など、特定の原因がある場合は、適切な歯科治療が必要です。
まとめ:違和感を放置せず、早めの相談を
「歯が浮く感じ」は、体からのサインです。「たいしたことない」と自己判断せず、まずは日々の歯磨きを丁寧に行ってみてください。
それでも症状が改善しない、繰り返す、あるいは歯茎の腫れや出血、痛みなどを伴う場合は、放置せずに早めに歯科医院を受診しましょう。早期に原因を突き止め、適切な対処をすることが、あなたの大切な歯を守ることに繋がります。
かかりつけの歯科医院で、定期的なチェックを受ける習慣をつけることをおすすめします。
にしあかし歯科
Tel:078-925-3333
2025年4月15日 カテゴリ:ブログ